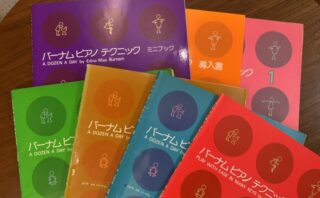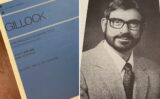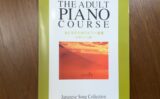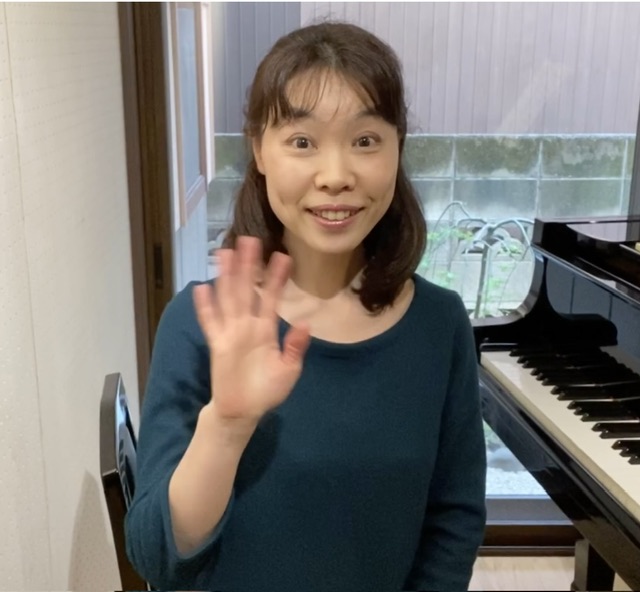人を惹きつける不思議な魅力と、人を狂わせる魔力を持つとされる「月」。
クラシック音楽には「月」にちなんだ曲がたくさん存在します。
今回は神秘的な「月」をイメージしながら演奏したい、おすすめのピアノ曲とピアノアレンジ楽譜を紹介します。
演奏難易度も合わせて書いてみました。
月光ソナタ/ベートーヴェン
ベートーヴェン作曲のピアノソナタ第14番。とても有名な第1楽章のみ、単独で演奏されることも多い曲です。
第1楽章で難しいのは、冒頭から何度も繰り返される右手の付点のリズム「ターンタ」と、左手の3連符のリズム「タタタ」のポリリズム。
また、複雑な中間部の和声の変化には少しずつ慣れていきましょう。
名曲集やピアノピースでは、第1楽章のみ収録されていることもあります。
ドレミ楽譜出版社「ピアノ名曲110選グレードB」
全音ピアノピース「月光の曲」
月の光/ドビュッシー
ドビュッシー作曲「ベルガマスク組曲」の第3曲目「月の光」。フランスの詩人ヴェルレーヌの詩「月の光」に影響されて作られた曲です。
原曲の演奏難易度は中上級〜上級ですが、弾きやすくアレンジされた大人におすすめの楽譜を紹介します。ハ長調アレンジです。
…とは言っても、この曲はもともとのリズムが単純ではないので、演奏難易度は初中級程度。
使用楽譜は、ドレミ楽譜出版社の「おとなのためのピノ曲集 クラシック編2」です。
がっつり原曲で弾きたいならば、全音ピアノピース「月の光/ドビュッシー」などで手に入れることができます。
月の光/フォーレ
フォーレ作曲の歌曲「月の光」。ドビュッシーと同じように、ヴェルレーヌの詩から作られた曲です。
ピアノは前奏から神秘的で、長めの前奏のあとの歌とのカラミがさらに素敵。
今回紹介するのはピアノソロアレンジの中でも弾きやすく、それでいてポリフォニーが美しいおすすめアレンジです。
原曲の変ロ長調から半音低い、比較的やさしいイ短調に移調されています。中間部は省略されて短めですが、右手で担当するピアノと歌の両方の二声で、それなりの難易度になります。
演奏難易度は中級程度でしょう。
使用楽譜は、ケーエムピーの「クラシックを弾きたくて 世界名歌編」。
月の光/ギロック
ギロック作曲の「月の光」は、24曲からなる叙情小曲集の11曲目です。
右手と左手ともに連続する3度は、ドビュッシーの「月の光」へのオマージュのよう。
シャープ5つのロ長調で、ダブルシャープや11連符やタイの連続もあり、譜読みにソルフェージュの力も必要です。
苦労して練習した先には美しい独特のハーモニーができあがります。大人のためと言っても良い、魅力的な小品です。難易度は、初中級〜中級程度。
ギロックの叙情小品集についての記事はこちら↓
使用楽譜は、全音の「ギロック 叙情小品集」
優雅な月よ/ベッリーニ
ベッリーニ作曲の歌曲「優雅な月よ」。
「ノルマ」「清教徒」など、美しいメロディが特徴のオペラで知られるベッリーニ。「優雅な月よ」は歌手がリサイタルで取り上げる機会が多い、定番の歌曲です。
ピアノソロアレンジは、単純で難しいところのない左手の伴奏と、自然なメロディの右手で構成されています。
これだけシンプルでいながら飽きのこないメロディ。素晴らしい作品だなぁと感じます。難易度は初級。
使用楽譜は、さきほどのフォーレの「月の光」と同じケーエムピーの「クラシックを弾きたくて 世界名歌編」。
荒城の月/瀧廉太郎
日本の歌からも紹介します。まずは、瀧廉太郎作曲の「荒城の月」。
「春高楼の花の宴…」からはじまる土井晩翠の詞があまりにも有名な、日本のクラシック曲です。
ちなみに、曲名の「荒城」はどこの城なのか?は諸説あるようですね。
「荒城の月のモデルは、仙台の青葉城だ」とか、「いや、会津の鶴ヶ城だ」…こども時代を仙台と福島で過ごした自分は、本当にそうかぁ???とどちらの説にも納得いかなかったものです。
青葉城には現存する天守閣がなくてイメージがわかないし、鶴ヶ城は真っ白くてピカピカでしたし(^◇^;)
おすすめのピアノレンジは、こちら。難易度は初中級程度。
使用楽譜は、ドレミ楽譜出版社「おとなのためのピアノ曲集 日本のうた編」です。
月の砂漠/佐々木すぐる
続いても、日本の歌から。佐々木すぐる作曲の歌曲「月の砂漠」。
こちらも日本歌曲の定番となっています。砂漠、美しい月、ラクダに乗った王子と王女…静かな情景が目に浮かぶようです。
「荒城の月」と同じく、ドレミ楽譜出版社「おとなのためのピアノ曲集 日本のうた編」のアレンジがおすすめです。難易度は初級。
楽譜についての詳細記事はこちら↓
朧月夜/岡野貞一
こちらも、誰もが知る日本のうた。岡野貞一作曲の「朧月夜」。
美しく響くピアノソロ 伝えたい日本のうたの編曲は、たっぷりとペダルを使って霞がかった月のような幻想的な響きを楽しめます。
1番と2番の対照的なアレンジが魅力的。難易度は初級。
使用楽譜→美しく響くピアノソロ 伝えたい日本のうた
宵待草/多忠亮
多忠亮作曲、竹久夢二作詞の歌曲「宵待草」。「今宵は月も出ぬそうな」の歌詞で知られます。
逆説的ですが、月が「見えない」ことによって、かえって大きな存在感を感じさせる曲です。
難易度は初中級。
使用楽譜は、ドレミ楽譜出版社「おとなのためのピアノ曲集 日本のうた編」です。